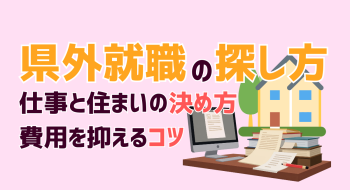\ 長野県求人数No.1 /
【後悔しない】地方の仕事探しで失敗しないコツ|20代〜40代必見の転職ノウハウを紹介!
- 地方の仕事探しで、リモートワークは最も経済的リスクの少ない選択肢です。
- 地方での生活は生活コストを大幅に削減でき、可処分所得を増やすことができます。
- 地方専門の求人サイトを利用すれば、地域密着型の仕事を効率的に探すことができます。

「地方には仕事がない」「今のスキルで本当に稼げるのか」そんな不安やネットの情報を前に、移住をためらっていませんか?
この記事を読めば、その漠然とした悩みは「地方でも自分らしく働ける」という具体的な確信に変わります。
公務員やリモート可能なIT職、地域を盛り上げる面白い仕事まで、多様な選択肢を網羅。
さらに、20代〜40代の年代別に見たリアルな収入事情や、あなたに合った仕事の探し方、活用できる移住支援制度まで詳しく解説します。
地方移住や転職のメリットとデメリットの両面にも触れているので、「理想と現実のギャップが不安…」という方にも安心の内容です。



この記事を読み終える頃には、理想の暮らしに向けた次の一歩がはっきりと見えているはずです。
地方でどんな働き方ができる?


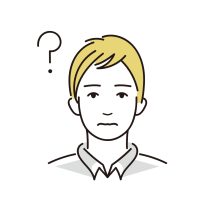
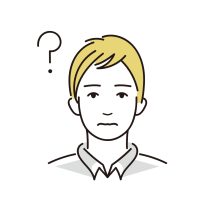
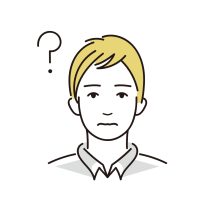
「地方には、どんな仕事があるんだろう?」
近年、テレワークの普及により働き方の選択肢が大幅に広がり、地方での仕事探しが現実的な選択肢となりました。



地方移住を考える20代から40代の方が抱える「地方に仕事がない」という不安は、実際には多くの選択肢が存在することで解消できます。
地方での働き方について、以下の内容を紹介します。
- 地元企業への就職・転職で安定した雇用を得る
- 地域おこし協力隊として地域活性化に貢献する
- 農業・林業・漁業などの第一次産業に従事する
- リモートワークで都市部の仕事を継続する
- 地方で独立・起業して新しい事業を始める
- 医療・介護職として地域の人々を支える
- 地方自治体の公務員として地域運営に携わる
地域に根ざして働く「地元企業」への就職・転職
地方企業への就職・転職は、地域に根ざした安定した働き方を実現する最もスタンダードな選択肢です。
多くの企業で後継者不足が課題となっており、2024年の調査では「後継者不在率」は62.15%で、前年(61.09%)から1.06ポイント上昇しています。
製造業、観光業、地域金融機関、IT企業などで年収300万円から500万円程度の求人が中心となっており、都市部で培ったスキルや経験を活かして重要な役割を担うチャンスが豊富にあります。
転職サイトやハローワーク、自治体の就労支援窓口を活用して情報収集を行い、移住前に内定を得ることで安心して地方生活をスタートできるでしょう。
移住の”お試し”にもなる「地域おこし協力隊」
地域おこし協力隊は、地方移住の入り口として最適で、年収約200万円の支援を受けながら最大3年間地域で活動できる制度です。
令和6年度は、10代から60代以上までの幅広い年齢層の総勢7,910名が活動しており、年齢制限も基本的に18歳以上であれば応募可能という間口の広さが魅力です。
隊員1人あたり報償費等が最大350万円、その他の活動経費が最大200万円、合計550万円が上限となっています。
任期後の定住率は、約70%と高い定着率を誇っています。
移住・定住、観光、商品開発、農林水産業、環境保全、デジタル、教育・文化など幅広い分野で活躍できるため、まずは「おためし地域おこし協力隊」で2泊3日の体験から始めることをおすすめします。
農業・林業・漁業など第一次産業に挑戦
農林・林業・漁業などの第一次産業は、自然と直接向き合う働き方で、都市部では得られない充実感と自給自足的な生活を実現できます。
地方の第一次産業は深刻な後継者不足に直面しており、新規参入者を歓迎する環境が整っているからです。
新規就農者向けの研修制度、農業ベンチャー企業での勤務、漁協での水産業従事など様々な選択肢があり、年収は200万円から400万円程度ですが、住居提供や研修支援制度が充実している地域が多数存在します。
林業においても山林の多い地域では主要な産業でありながら後継者不足が顕著で、就職のチャンスが豊富にあります。



まずは各自治体の新規就農支援制度や体験プログラムに参加し、実際の作業を体験してから本格的な参入を検討しましょう。
収入の不安を解消する「リモートワーク
リモートワークは、収入を維持しながら地方の豊かな自然環境で働ける、最も経済的リスクの少ない地方移住の選択肢です。
2024年7月時点でも週3日以上の出社頻度は定着しているものの、コロナ前と比較して柔軟な働き方も一定程度許容されており、正社員の約22.6%がリモートワークを実施しています。



ITエンジニア、Webデザイナー、ライター、コンサルタント、営業職などがリモートワークに適しており、最近では従来の仕事をそのままに住む場所だけを変える「転職なき移住」も増加傾向です。
移住前に勤務先とリモートワーク可能な日数や条件を明確に取り決め、インターネット環境の整った移住先を選ぶことが成功の鍵となります。
自分の夢を形にする「地方での独立・起業」
地方での起業は、低コストで事業を始められ、地域の課題解決にも貢献できる魅力的な働き方です。
地方は東京などの都会よりも人件費や家賃などが安いため、起業にかかるコストを大幅に削減でき、起業への支援を行っている自治体も多く存在するのです。
例えば、長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業では、地域の課題解決を図る事業の創業予定者に対し最大200万円を支援するなど、各地で手厚い支援制度が用意されています。
カフェ、ゲストハウス、農産物加工、地域PRコンサルティングなどの事業で成功例が多数報告されており、都市部と比較して競合が少なく地域密着型のビジネスモデルを構築しやすい環境があります。



まず移住先の自治体の起業支援制度を詳しく調査し、地域のニーズを把握してから事業計画を立てることが重要です。
地域に深く貢献する「医療・介護職」
医療・介護職は、地方で最も求められている職種の一つで、安定した雇用と地域貢献を両立できる働き方です。
地方の高齢化が進む中、医療・介護従事者の不足は深刻な社会問題となっており、看護師、介護士、保育士、理学療法士などの有資格者は地方でも都市部と同等またはそれ以上の待遇で迎えられることが多くあります。
看護師の場合、年収350万円から500万円程度で、住宅手当や移住支援金が支給される病院も多数存在し、地方の総合病院や特別養護老人ホーム、訪問看護ステーションなど幅広い求人があるのです。



医療・介護系の専門転職サイトや自治体の保健福祉課に相談して、移住支援とセットになった求人情報を収集することをおすすめします。
地域運営の担い手「地方公務員」という道
地方公務員は、安定した雇用と地域社会の発展に直接関われるやりがいを両立できる働き方です。
地方自治体では地方創生や人口減少対策のため、多様な経験を持つ人材を積極的に採用しており、年齢制限の緩和や社会人経験者枠の拡大など、民間企業経験者にとって転職しやすい環境が整えられています。
市役所の企画課、観光課、農政課、地方議会事務局などで年収300万円から450万円程度の待遇が一般的で、民間企業での経験を活かして地域の課題解決に取り組むポジションが増加しています。
地方公務員の仕事内容は事務職から土木、福祉、防災まで多岐にわたり、各自治体の採用情報をチェックし、社会人経験者向けの試験制度や任期付職員制度を活用することで転身の道が開けるでしょう。
\ 長野県求人数No.1 /
地方で仕事をするメリットとは?


都会の暮らしも良いけれど、地方で働くことには、それを上回る魅力があるかもしれません。
2024年の移住相談件数は61,720件と前年から4.1%増加し、4年続けて過去最高を更新したことからも分かるように、地方での仕事に対する関心は高まり続けています。
地方で仕事をするメリットは、主に以下の内容が挙げられます。
- 満員電車からの解放で通勤ストレスが大幅に軽減される
- 家賃や生活費を大幅に削減できる
- 豊かな自然環境の中で心身ともに健康的に働ける
- 地域の人々との温かいつながりを築ける
- 低コストで起業や副業にチャレンジしやすい
朝の憂鬱から解放される「通勤ストレスの軽減」
地方での仕事は、都市部特有の満員電車や長時間通勤から解放され、心身の健康とワークライフバランスを大幅に改善できます。
都会では公共交通機関の利用が主流で朝夕のラッシュ時には電車やバスが混雑しますが、地方ではマイカー通勤が一般的で移動時間も短縮されます。
東京圏では平均通勤時間が片道1時間を超えることも珍しくありませんが、地方では片道15分から30分程度で職場に到着できることが多く、1日あたり1〜2時間の時間創出が可能です。



通勤で満員電車に乗る必要もなくなるため、ゆとりあるライフスタイルでストレス軽減が期待でき、その分の時間を家族との時間や趣味、自己啓発に充てることで生活の質が大幅に向上するでしょう。
お金にゆとりが生まれる「生活コストの削減」
地方での生活は住居費を中心に生活コストを大幅に削減でき、同じ年収でも実質的な可処分所得を増やすことができます。
東京都世田谷区の家賃相場が1Kと1DKで10万円〜13.7万円なのに対し、長野県長野市の家賃相場は1Kから1DKで約5.4万円と、およそ2分の1も相場が安くなっています。
生活費は都会と比べて約2割減程度で考えておくのが良いとされており、特に家賃削減効果は絶大です。



都市部で月15万円の家賃を支払っていた場合、地方では同程度の住環境を月5万円程度で確保でき、年間120万円の節約が可能になります。
生活コストの削減により、貯蓄や投資、子どもの教育費など将来への投資に回せる資金が増加し、経済的な余裕は精神的な安定にもつながりますよ。
心豊かになる「すぐそばにある自然」
地方では豊かな自然環境に囲まれながら働くことで、ストレス軽減と創造性の向上を実現できる理想的な職場環境を手に入れることができます。
地方移住の最大のメリットは自然の豊かさを感じられることで、都会の整備された街並みも素敵ですが、緑豊かな自然の中でゆっくり過ごしたい方には田舎暮らしが最適です。



仕事帰りに気軽に温泉に立ち寄ったり、休日は家族でアウトドアを楽しんだりと、田舎ならではの体験を楽しむことができます。
またアウトドアな趣味をお持ちの方には特にメリットが大きく、キャンプやサーフィンなどの趣味も気軽に楽しめる環境が整っています。
自然豊かな環境での勤務は都市部では得られない心の豊かさと健康的なライフスタイルを提供し、四季の変化を感じながら働くことで仕事に対する新たな価値観や働き方を発見できるでしょう。
暮らしに温かみが増す「地域社会とのつながり」
地方では地域コミュニティとの密接なつながりを築くことができ、仕事面でも人生面でも豊かな人間関係を構築できます。
地方の場合、人同士のつながりや関係性を大切にする文化が根強く残っており、地域の行事やイベント、コミュニティなども多いため交友関係が広がっていきます。
都会では希薄になりがちな人間関係も、田舎に移り住むとご近所付き合いなどで関係を深める機会が多くなるという特徴があるのです。
近隣の方から野菜をもらったり、地域ならではの行事に参加できるなど、地方でしか味わうことのできない体験がたくさんあります。
また地域のお祭りや清掃活動、子どもの見守り活動などを通じて、仕事以外での充実したコミュニティ活動に参加できます。
地域社会とのつながりは単なる人間関係を超えて、地方での仕事や生活を支える重要な基盤となり、困った時に助け合える関係性は都市部では得難い貴重な財産となるでしょう。
地方で広がるチャンス「起業や副業に挑戦しやすい環境」
地方は低コストで起業や副業にチャレンジできる環境が整っており、新しいビジネスを始めるハードルが都市部より格段に低くなります。
地方は東京などの都会よりも人件費や家賃などが安いため、起業にかかるコストを削減できるのです。
起業の支援を行っている自治体も多く、これらの制度を利用すればさらにコストを抑えられるでしょう。
カフェ、ゲストハウス、農産物加工、地域PRコンサルティングなど、地域の特色を活かした事業で成功例が多数報告されています。



また競合が少ないため、地域密着型のビジネスモデルを構築しやすい環境です。
地方での起業や副業は低リスクで新しいチャレンジができる絶好の機会で、都市部では実現困難なアイデアも地方なら地域のニーズと組み合わせて現実的なビジネスとして展開できる可能性があります。
\ 長野県求人数No.1 /
地方で仕事をするデメリットとは?





もちろん、地方での仕事には良いことばかりではありません。
地方移住への関心が高まる一方で、現実的な課題を理解しておくことが成功する移住の鍵となります。
地方での仕事をする場合のデメリットは、以下の内容が挙げられます。
- 都市部と比べて給与水準が低めに設定されている
- 職種や業界の選択肢が限られ希望職種が見つかりにくい
- 公共交通機関が限られ車なしでは生活が不便になる
- 最新の情報やビジネストレンドの流入が遅れがち
- 転職市場が狭く次のキャリアステップが限定的
多くの人が気になる「給与水準の変化」
地方の給与水準は都市部と比較して低い傾向にあり、年収で100万円以上の差が生じることが一般的です。
最も平均年収が高い東京都では471万円となっている一方、地方では年収400万円台の県も多く存在します。
神奈川県452万円、千葉県435万円、埼玉県426万円、茨城県424万円とトップ5を関東の都県が占めており、関東圏が給与水準で明らかに優位に立っています。
都市部と地方では収入の差があるのは事実ですが、その分支出の差もあるため生活水準や生活の満足度はさほど変わらないことが分かっています。
しかし都市部に比べて地方は年収を上げづらいという特徴もあり、地方在住者は年齢の割に生活水準が上がらない場合があることも事実で、長期的なキャリア形成には注意が必要です。
キャリアの選択肢は?「希望の職種が見つかりにくい可能性」
地方では都市部と比較して職種の選択肢が限られており、特に専門性の高い職種や新興業界の求人が少ない傾向があります。
地方の産業構造は製造業、農業、観光業、医療・介護などが中心となることが多く、IT関連やコンサルティング、金融など都市部に集中する業界の求人は限定的です。
WebデザイナーやITエンジニア、マーケティング職などの専門職は、地方では企業の規模や案件数が限られるためキャリアの幅を広げにくい場合があります。
一方で看護師や介護士、公務員、地域密着型のサービス業などは地方でも安定した需要があります。
希望職種が地方で見つからない場合は、リモートワークでの就業や、地方の産業に合わせたスキルチェンジを検討することが現実的な選択肢と言えるでしょう。
移動手段の確保は必須?「車社会が基本の暮らし」
地方では公共交通機関が限られるため、車が生活必需品となり維持費として年間30万円から50万円の追加コストが発生します。
一部の地方都市中心部を除き、移動手段は車であることがほとんどで、移住相談では地元民からまず「自動車は絶対必要」と言われる状況です。
日常の買い物、通勤、医療機関への通院などすべてに車が必要になり、地方では電車やバスの本数が限られているため車なしでは行動範囲が大幅に制限されます。
軽自動車でも月額約3万1000円から3万7000円、小型自動車では約3万7000円から4万4000円、普通自動車では約4万3000円から5万1000円の維持費がかかります。
都市部で車を持たない生活をしていた人にとって、ガソリン代、保険料、税金、車検代などを含めた維持費は大きな家計負担となるため、移住予算に組み込んでおくことが重要です。
スキルアップは大丈夫?「情報やトレンドとの距離感」
地方では最新のビジネストレンドや業界情報の流入が都市部より遅く、キャリア形成や事業展開において情報格差が生じる可能性があります。
多くの企業の本社機能や研究開発拠点が都市部に集中しているため、新しいビジネスモデルや技術動向、市場の変化などの情報は都市部から徐々に地方に波及する傾向です。
スタートアップ企業の動向、新しいマーケティング手法、DX関連の最新技術、投資トレンドなどの情報は都市部では日常的に触れられますが、地方では数か月から半年程度遅れて浸透することがあります。
業界のネットワーキングイベントや勉強会なども都市部での開催が多く、直接的な情報交換の機会が限られるため、業界の最前線で活躍したい人にとっては大きなハンディキャップとなる可能性があるのです。



オンラインでの情報収集やウェビナー活用で情報格差を最小限に抑える工夫が必要です。
次のステップは?「転職市場の規模」
地方では転職市場が狭く、キャリアチェンジや昇進の機会が都市部と比較して限定的になります。
地方は企業数が少なく、同じ業界・職種での転職先が限られるため、キャリアアップや待遇改善を目的とした転職が困難な場合があるのです。
IT業界であれば都市部では数十社から数百社の選択肢がありますが、地方では数社程度しか存在しない場合があります。



また同じ地域内での転職は人間関係の問題が生じやすく、選択肢がさらに狭まることがあります。
現在の職場に不満があっても同じ地域内では転職先が見つからず、結果的に都市部への再移住を検討せざるを得ないケースも。
特に管理職レベルのポジションは非常に限られており、キャリアの頭打ちを感じる可能性があるため、移住前に長期的なキャリアプランを立てておくことが重要です。
\ 長野県求人数No.1 /
地方移住者のリアルな仕事と収入事情


では、実際に移住した人たちは、どんな暮らしをしているのでしょうか。
地方移住の3つの事例を通じて、仕事や収入の変化について紹介します。
- IT職30代男性の年収変化と満足度
- 介護職の収入状況
- 起業した40代夫婦の収入と暮らしの実態
IT職30代男性の年収変化と満足度
例えば、東京から札幌へ地方移住するIT職30代男性の場合、年収は600万円から450万円へと150万円減少することが想定されます。
しかし、家賃や食費、交際費などの生活費が3分の2ほどに削減される可能性が大きく、実質的な手取りには大きな変化がありません。
2025年現在、ITエンジニアの転職市場は引き続き売り手市場となっており、リモートワークが可能な求人も増加傾向にあります。
マイナビIT AGENTでは約4,000件、レバテックキャリアでは約1万件のリモートワーク対応求人が確認でき、地方に住みながらも都市部の企業で働ける機会が拡大しています。



ワークライフバランスの向上と自然豊かな環境での暮らしという付加価値を考慮すると、満足度の高い移住事例といえるでしょう。
介護職の収入状況
介護職全体の平均月給は338,200円となっており、一般労働者全体の平均月給330,400円を上回る水準です。
介護福祉士専門員になれば、平均月給は374,410円に達し、無資格介護士と比較すると約3〜4万円高い給与を実現できます。
2024年6月からの介護報酬改定により処遇改善が実施され、改定率1.59%のうち0.98%が介護職員の処遇改善に充てられています。
介護業界は深刻な人材不足に直面しており、若い人材への需要が非常に高く、20代の転職者は歓迎される環境が整っています。
地方移住と組み合わせることで、都市部より低い生活コストで質の高い暮らしを実現でき、資格取得によるキャリアアップも期待できる魅力的な選択肢です。
起業した40代夫婦の収入と暮らしの実態
北海道中札内村へ移住した40代夫婦の事例では、夫がJR東海のリニア中央新幹線プロジェクトから転身し、移住後2年で起業を果たしています。
地方での起業は都市部と比較して初期投資を大幅に抑制でき、物件の家賃や食費などの生活コストも安いため、挑戦しやすい環境が整っています。
地方では様々な業界で人手不足が深刻化しており、空き家対策や高齢者向けサービス、観光振興といった地域課題を解決するビジネスには行政との連携協定も期待できます。
都市部で数百万円から数千万円規模の資金調達が必要な起業と比べ、地方では小さな取り組みから事業を開始でき、倉庫や古民家などの物件も交渉次第で低コストでの活用が可能です。
豊富なキャリア経験を地方の課題解決に活かしながら、新たな人生を築ける絶好の機会といえます。
\ 長野県求人数No.1 /
地方の仕事探しで失敗しない5つのステップ
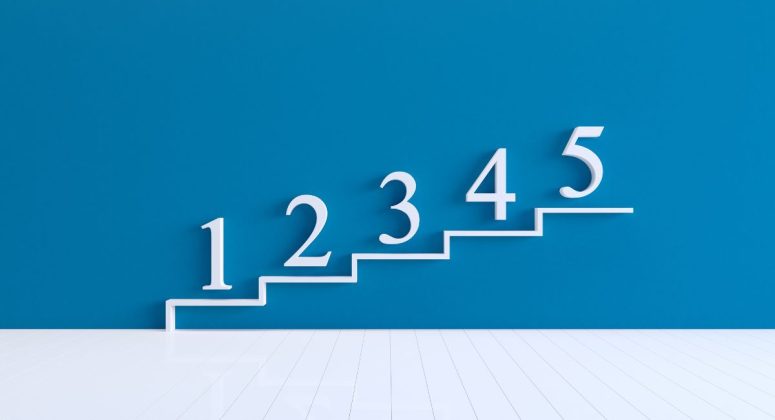
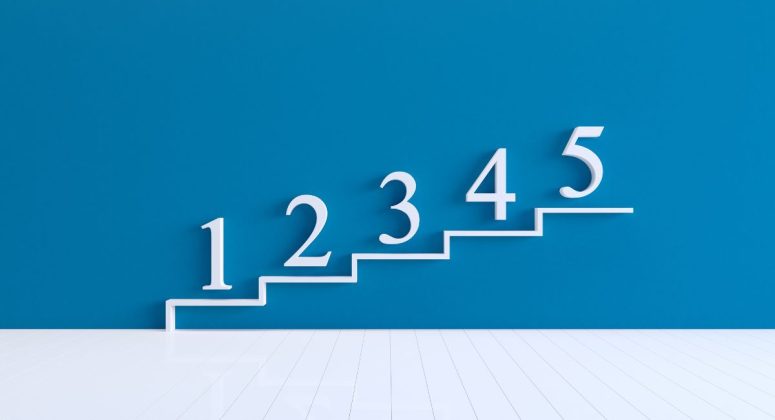
移住への思いが固まってきたら、次はいよいよ具体的な仕事探しです



地方での仕事を見つけるまでの5つのステップを見ていきましょう。
- 移住先候補を複数選定する
- ハローワークで地元求人を調査する
- 自治体の移住相談窓口を活用する
- 地方専門の求人サイトに登録する
- 現地で面接・職場見学を行う
STEP1:まずは情報収集。「移住先の候補」をいくつか見つける
2024年の移住希望地ランキングでは群馬県が1位、静岡県が2位、栃木県が3位となっており、都市部へのアクセスが良い県が人気を集めています。
地方移住で最も多い相談が「仕事があるか」という点で、選ばなければ人手不足の仕事はたくさんありますが、希望条件を増やすほど選択肢は狭まります。
そのため移住先選定では、仕事の選択肢と生活環境のバランスを考慮して複数の候補地を比較検討することが重要です。
地域によって産業構造や給与水準が大きく異なるため、仕事の選択肢、アクセスの良さ、支援制度の充実度、生活コストの4つの観点から最低3つの候補地を絞り込み、それぞれの特徴を詳細に調査することをおすすめします。
STEP2:地元のリアルを知る。「ハローワーク」で求人調査
ハローワークは地方の求人情報を網羅的に把握できる最も確実な手段で、地元密着型の中小企業や地方公務員の求人情報が豊富に集まっています。
地方は都会に比べて賃金が安くなる傾向がありますが、住居費や食料品などの物価も安いため、転職先を探す際には住環境も考慮することが重要です。
ハローワークでは給与だけでなく地域の生活コストを踏まえた相談も可能で、北海道庁が開催する「北海道とつながるカフェ」のように、自治体とハローワークが連携した就職支援も活発化しています。
インターネット検索だけでなく、実際に現地のハローワークを訪問して相談員との面談を通じて、求人票に記載されていない職場の雰囲気や地域の就職事情も把握することが成功の鍵となります。
STEP3:頼れる味方を見つける。「自治体の移住相談窓口」を訪ねる
2024年の移住相談件数は過去最多の61,720件となり、4年連続で相談者が増え続けており、自治体の移住相談窓口は仕事探しと生活支援をワンストップで提供する重要な拠点となっています。



移住施策に力を入れて丁寧な対応を行っている県がランキング上位に入る傾向があり、自治体は移住者確保のため仕事紹介から住居確保まで総合的な支援を強化しています。
国や地方自治体では移住支援金、就業マッチング補助、住宅取得補助などの制度が充実。
仕事探しだけでなく住居確保や子育て支援など生活全般のサポートが受けられるため、移住検討の初期段階から積極的に活用し、現地との関係性を構築することが重要です。
STEP4:効率的に求人情報を探せる。「地方専門の求人サイト」に登録する
地方移住や田舎暮らしを希望する人をターゲットとした求人サイトを利用すれば、都市部では見つからない地域密着型の仕事を効率的に探すことができます。



2023年の調査では全体の6割が地方移住に興味があると回答し、その理由として「転職をせずに地方へ引っ越しができる」が55.0%となっており、リモートワーク対応の求人需要が高まっています。
地方特化求人サイト、UIターン支援サービスがあり、
複数のサイトに同時登録することで求人の取りこぼしを防ぎ、希望条件に合致する案件の通知機能を活用してタイムリーな応募につなげることが成功のポイントです。
STEP5:最後は自分の目で確かめる。「現地での面接・職場見学」
移住前に描く理想と実際の地方暮らしではギャップがあり、移住前にそのギャップをどれだけ埋められるかが成功の鍵となります。
想定内のギャップであればダメージは少ないものの、想定外のダメージは移住直後から大きな問題となるため、現地での面接・職場見学は移住後のギャップを最小限に抑える最も重要なステップです。
全国で移住体験ツアーや仕事付き移住プランなど「就職保証」のある自治体の体験プログラムが実施されており、実際の職場見学では働く人たちの表情や職場の雰囲気をチェックできる貴重な機会となります。
面接だけでなく職場見学、地域住民との交流、実際の生活体験を組み合わせた3日間程度の滞在プランを組み、移住後の生活を具体的にイメージできる情報収集を行うことが失敗しない移住の秘訣です。
\ 長野県求人数No.1 /
地方移住前に確認すべき5つのポイント
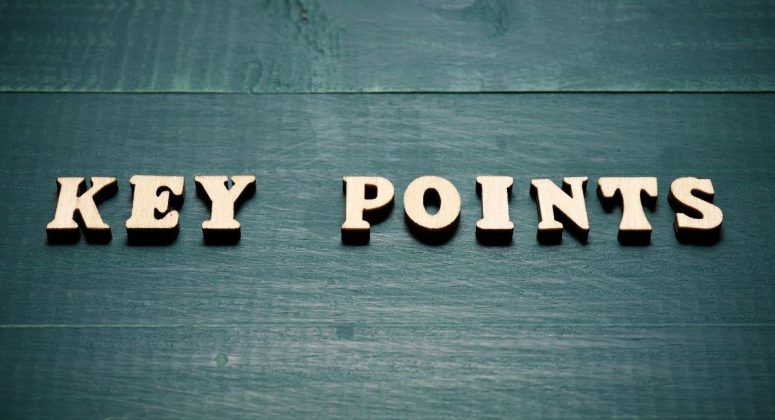
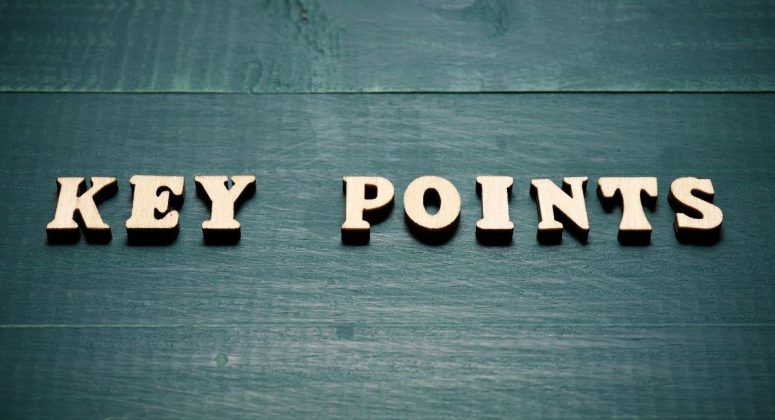
いよいよ移住先が具体的に見えてきたら、契約書にサインする前に、最終チェックをしておきましょう。



憧れだけで突っ走ってしまうと、思わぬ落とし穴があるかもしれません。
ここでは、後悔のない移住のために、必ず確認しておきたい5つのポイントを解説します。
- 希望職種の求人数と給与相場
- 住まいの確保状況と家賃水準
- インフラ・交通の利便性
- 子育てや教育環境の整備度
- 災害リスクと防災体制
Point1:仕事について ― 希望の働き方は実現できそうか?
地方移住に関する相談で最も多いのが「地方に仕事はありますか」という質問です。
選ばなければ人手が足りていない仕事はたくさんありますが、希望する職種や条件を増やせば増やすほど都会よりも選択肢は少なくなります。
年収を落とさずに地方移住することは比較的難しく、特に中上流階層の移住希望者が現在の収入水準を維持するには、専門性が必要となることが多いです。
東京から札幌へ移住したIT職30代男性の場合は年収が600万円から450万円へ減少した一方、介護職全体では平均年収よりも多い収入を得ることができる可能性があるなど、職種により大きく異なります。
希望職種の求人数を複数の求人サイトで調査し、地域間の給与差を比較して現実的な収入予測を立てることが重要です。
Point2:住まいについて ― 安心して暮らせる家は見つかるか?
近年、地方では過疎化により空き家が増加し、物件価格も低下傾向にあります。



インターネットで地方物件が検索できるようになり、住まいの確保は以前より容易になっています。
東京から地方移住した事例では「家賃、食費、飲み会などの生活費が3分の2になった」ように、住居費削減が地方移住の大きなメリットです。
地方では物件費用が相対的に低く、好条件で広いスペースを借りることも可能で、交渉次第では倉庫や古民家を低コストで活用できます。
また、移住支援金、家賃補助、住宅取得補助などの自治体支援制度も充実しています。



空き家バンクや地方不動産サイトで実際の物件価格を調査し、移住支援制度と組み合わせた住居費シミュレーションを行うことで、生活コスト削減効果を具体的に把握できますよ。
Point3:インフラ・交通の利便性について ― 緊急時を含めた移動手段を複数確保できるか?
2024年の移住希望地ランキング上位には、都市部へのアクセスが良い群馬県や栃木県、大都市がある福岡県や宮城県がランクインしており、インフラ・交通の利便性は移住先選定の重要な判断基準となっています。



2024年7月時点で週3日以上の出社が定着し、テレワークの柔軟性が許容されていても、完全リモートでない場合は都市部への通勤手段が必要です。
札幌移住者の「東京に遊びに行くのに交通費がかかるのはマイナス」という声のように、都市部との距離は移住後の生活に直接影響します。
地方でリモートワークや副業、起業などの働き方を実現したい場合、インターネット環境の整備状況も重要な要素です。
公共交通機関の運行状況、高速道路・空港へのアクセス、インターネット回線の品質を事前に調査し、緊急時を含めた移動手段を複数確保できるかを確認することが必要です。
Point4:子育てについて ― 家族みんなが笑顔で暮らせるか?
地方自治体では移住者確保のため、保育料無償化や教育費助成など家族帯同向けの支援制度が充実している一方、教育の選択肢や質については地域差が大きく、子育て世代は特に慎重な事前調査が必要です。
40代は家庭を持っている人も多く、子どもの教育費を考えると収入減少が不安要素となる中で、地方移住のメリットを活かすには教育環境の質と経済性の両立が重要です。
地方では都市部と比較して教育の選択肢が限られる場合があるため、事前の詳細な調査が欠かせません。
2025年版の移住補助金・支援制度ランキングでは、子育て支援に力を入れる自治体が上位にランクインしており、保育料補助や医療費援助などの制度が充実しています。
保育園・学校の空き状況、教育水準、習い事の選択肢、医療機関の充実度を調査し、子どもの年齢に応じた教育プランと支援制度を組み合わせた総合的な判断を行いましょう。
Point5:災害リスクと防災体制について ― 災害時の対応策を家族で共有しておくことが重要
地方移住では自然災害のリスクと防災体制の確認が重要で、特に気候変動により災害の頻度・規模が拡大している現在、移住先の災害リスクと地域の防災体制を事前に把握することが安全な暮らしの前提条件です。
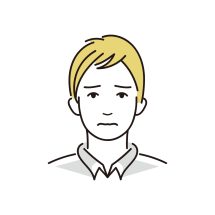
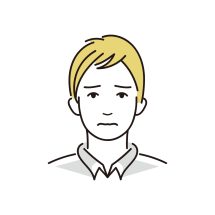
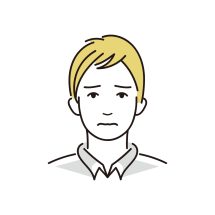
地方では都市部と比較して避難場所までの距離が長い、医療機関が少ない、道路の復旧に時間がかかるなど、災害時の対応に制約がある場合があります。
2024年の移住希望地ランキングで上位の群馬県、静岡県、栃木県でも、それぞれ地震リスク、火山リスク、豪雨リスクなど異なる災害特性があります。
地域によって地震、台風、豪雨、豪雪など、リスクとなる災害の種類が大きく異なるため、自治体のハザードマップや防災計画、避難所の整備状況、地域の防災訓練実施状況などの確認が必要です。
国土交通省のハザードマップポータルサイトで災害リスクを確認し、移住候補地の自治体が公表する防災計画・避難場所・備蓄状況を調査して、災害時の対応策を家族で共有しておくことが重要です。
\ 長野県求人数No.1 /
地方移住支援制度を活用する方法





地方移住を考えるとき、経済的な不安はつきものです。



でも、心配しないでください。
国や自治体には、あなたの新しいスタートを応援してくれる、たくさんの支援制度が用意されています。
ここでは、知っていると知らないとでは大違いの、お得な制度の上手な活用方法をご紹介します。
- 移住支援金の対象条件を確認する
- 起業支援制度を調べて活用する
- 住宅関連の補助金を利用する
- 移住就職マッチングイベントに参加する
まずは基本の「移住支援金」。自分は対象になるか確認しよう
国や地方自治体では移住支援金、就業マッチング補助、住宅取得補助などの制度が充実しており、最大100万円の移住支援金を受給できる可能性があります。
2023年の調査では移住支援金の存在を知らない割合が約65%と認知度は低いものの、制度の内容を知った上で約60%の回答者が「魅力がある」と回答しており、制度を知ることで移住のハードルが下がる効果があるでしょう。
東京圏から地方への移住者に対して最大100万円(単身者60万円、世帯100万円)の移住支援金が支給される制度があり、対象となる自治体や企業での就業、起業などの条件を満たす必要があります。
移住支援金の受給には東京圏での一定期間の居住や対象企業への就職などの条件があるため、移住検討段階で自治体の公式サイトや移住相談窓口で詳細な対象条件を確認し、受給可能性を事前に把握することが重要です。
起業支援制度を調べて活用しよう
地方では都会と比べて初期投資を抑制でき、家賃や食費などの生活費も安いため挑戦しやすい環境が整っており、特定の地域課題を解決するビジネスでは行政との連携協定も期待できます。
地方では地域活性化のため起業を支援している自治体があり、事業再構築補助金や地域創生起業支援金などの制度が用意されているのです。



様々な業態が人手不足で悩んでいるため、そこを補填するサービスの立ち上げや、インターネットを使った地方商品販売の仕組み作りなど、アイデア次第で形にできる機会があります。
北海道へ移住した40代夫婦の事例では、2年で起業を果たした成功例もあり、都会で数百万円規模の資金調達が必要な起業と比べ、地方では小さなことから仕事を始められ、物件費用も相対的に低く、交渉次第で倉庫や古民家を低コストで活用できます。
家賃やリフォーム代も!見逃せない「住宅関連の補助金」
東京から地方移住した事例では「家賃、食費、飲み会などの生活費が3分の2になった」ように住居費削減が地方移住の大きなメリットで、さらに住宅関連の補助金を活用することで初期費用と継続的な住居費負担を大幅に軽減できます。
近年、地方では過疎化により空き家が増加し、物件価格も低下傾向にある中で、自治体は移住者確保のため住宅関連の支援制度を強化しています。
移住支援金、家賃補助、住宅取得補助などの制度が各自治体で用意されており、移住すると無料で住める家がもらえる0円物件など手厚い住宅支援がある自治体や、家賃1万円の空き家バンクなどの制度もあるのです。
ただし、0円物件などには以下のデメリットがあるので、注意が必要です。
- 手続きに手間がかかる。
- 税金がかかる。
- リフォームや立て直しに予想以上に費用がかかる可能性がある。
住宅関連補助金は自治体により内容が大きく異なるため、移住候補地の空き家バンクや住宅支援制度を比較検討し、賃貸・購入・改修それぞれのパターンで利用可能な補助金を整理して、最も経済的メリットの高い住居確保方法を選択しましょう。
移住就職マッチングイベントに参加しよう
2024年の移住相談件数は過去最多の61,720件となり、4年連続で相談者が増え続けている状況で、移住就職マッチングイベントは企業と移住希望者を効率的に結びつける重要な機会となっています。
移住してから後悔することのないよう、説明会や求人をチェックして地方移住のビジョンをより明確にすることが重要で、マッチングイベントは移住前のギャップ解消に有効です。
北海道庁では移住希望者向けに定期的に「北海道とつながるカフェ」というイベントを開催しており、オンラインと東京会場で同時開催するなど、各自治体が積極的に開催しています。
移住体験ツアーや仕事付き移住プランなど、「就職保証」のある自治体の体験プログラムと連動したマッチングイベントも開催されており、最新の支援制度情報も同時に入手できるメリットがあります。



事前に参加企業をリサーチし、自分のスキルや経験をアピールできる準備をした上で参加することで、効果的な情報収集と企業とのネットワーク構築を実現できるでしょう。
\ 長野県求人数No.1 /
まとめ


本記事では、地方での多様な仕事の選択肢から、移住者のリアルな収入事情、具体的な仕事の探し方までを網羅的に解説しました。



「地方には仕事がない」という漠然とした不安は、IT職や専門職、起業といった多様な働き方を知ることで、解消されたのではないでしょうか。
重要なのは、思い込みを捨てて正しい情報を集め、行動することです。
自分のスキルやこれまでのキャリアを活かせる仕事が、地方にも数多く存在します。
特に長野県などは、移住支援が手厚く、ITやものづくりなどに特化した求人も豊富です。
地域に詳しい移住エージェントを活用することで、ミスマッチのない仕事探しが実現できます。



この記事で紹介した仕事探しのステップや支援制度を参考に、まずは気になる自治体の移住相談窓口に連絡したり、地方専門の求人サイトを覗いたり、小さな一歩から始めてみてください。
あなたの理想の働き方と暮らしは、その行動の先にきっと待っています。