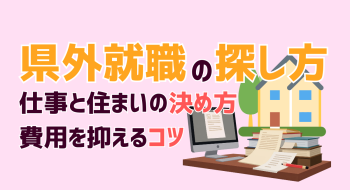\ 長野県求人数No.1 /
地方創生企業の取り組み事例|大手からベンチャーまで成功要因を分析
- 成功の鍵は、地域との信頼関係と、持続可能な収益モデルの両立です。
- 「企業版ふるさと納税」や「中堅企業向け賃上げ促進税制」など、大きな財務メリットを享受できます。
- 多額の初期投資が必要な一方で、投資回収期間が長期にわたるため、財務負担が重くなります。

うちも参入したいけれど、どう始めればいいのか分からない…。



地方創生に取り組む企業が急速に増加している今、どのように始めればいいかと悩んでいませんか?
石破首相による2025年度予算倍増計画で注目が集まる中、成功事例を知らずに参入して失敗するリスクを避けたいのは当然です。
この記事では、アソビューやリノベるなど実際に成果を上げている企業の取り組み事例から、企業版ふるさと納税や補助金制度の効果的な活用方法、自治体との連携ステップまで、あなたの会社が地域活性化で成功するための具体的なロードマップをお伝えします。
地方創生に取り組む企業の特徴と分類


この章では、地方創生に取り組む企業の特徴と分類をわかりやすく解説します。
2025年は政策支援の拡充により参入環境が整い、企業の動きが加速しています。
- 大手企業:複数地域にまたがる横断的プロジェクトの展開
- IT・テック企業:データ・AI・クラウド等を活用した地域課題の解決
- 地域密着型企業:地域資源を起点にした持続可能な収益モデルづくり
特徴(1)大手企業とベンチャー企業の違い
大手とベンチャーでは、地方創生への向き合い方が異なります。
KDDIや日立システムズなどの大手は、資金力と展開ノウハウを武器に、複数地域でスマートシティやデジタルインフラを並行して進めます。
一方、面白法人カヤックのようなベンチャーは、住民参画型で鎌倉に根差したプロジェクトを展開し、地域特性を踏まえた小回りの利く実装が強みです。
政府・自治体・企業・市民の連携が進む中で、企業は自社の規模と強みを踏まえた戦略の選択が重要です。
特徴(2)IT・テック企業の地方創生アプローチ
IT・テック企業は、DX(デジタルトランスフォーメーション)で地方創生の効率化を図っています。



老朽システムへの依存や人手不足が課題となる中、デジタル活用は不可欠です。
アソビュー株式会社は鳥取県での「体験×WEB」による地域活性化を成功させ、業務効率化やWEB改修、電子チケット導入などの事例を全国に展開しています。
ソフトバンクは自治体DX推進サイト/取り組み群「ぱわふる」で、クラウドやAI等のソリューションと事例を束ねて自治体を支援し、ユニリタグループは車載器・乗降カメラ等で収集した運行・乗降データの可視化・分析し、バス運行の最適化と地域活性化の両立を支援しています。
これらの企業は、地域の具体的な課題を理解し、住民や自治体のニーズに合わせたカスタマイズされたデジタルソリューションを提供することで成果を上げているのです。
特徴(3)地域密着型企業の取り組み特徴
地域密着型企業は、地元の信頼関係と地域資源の深い理解を基盤とした持続可能な地方創生を推進しています。
需要はある一方で、人手不足と高齢化により供給が追いつかない状況で、地域密着企業の役割が増しているのです。
ローソン株式会社は地域ごとのニーズに応じた商品開発を進め、地元の農産物や加工品を積極的に取り入れることで地域経済の循環を促進しています。
リノベる株式会社は築48年の電話局をシェアキッチンやブルワリー、ダンススタジオなどが入る地域参加型複合施設として再生するなど、地域資源を最大限に活用したプロジェクトを展開しています。
建設業界でも地場産業の振興や観光資源づくりが広がっており、地域貢献の深度が競争力に直結しやすい点が特徴です。
\ 長野県求人数No.1 /
分野別にみる地方創生企業の事例


この章では、主要分野ごとに企業の取り組みと成功事例を紹介します。
2025年は政策支援の強化で企業参入が活発化。特に次の4分野で動きが見られます。
- 観光・まちづくり:体験型サービスと地域ブランディング
- 不動産・住宅:空き家活用とリノベーション
- 人材・雇用創出:マッチングと人材育
- 農業・一次産業支援:スマート農業とアグリテック
事例(1)観光・まちづくり分野の主要企業
観光・まちづくり分野では、デジタル技術と地域資源を組み合わせた体験型サービスを提供する企業が地方創生の牽引役となっています。
アソビュー株式会社は「体験×WEB」で予約・券売・サイト改修などのデジタル化を進め、鳥取県の取り組みを全国各地へ横展開している状況です。
株式会社trippieceは、テーマ性のある旅行マッチングで地方の魅力発掘に貢献しています(リピート率等の数値は時期・公表状況により変動)。
大阪・関西万博では大規模ドローンショーなどの先端演出が予定され、自治体イベントでも実施例が増えています。



観光プロモーションの手法として注目が高まっています。
これらの企業は、集客だけでなく住民協働を重視し、持続可能な観光モデルの構築に取り組んでいるのです。
事例(2)不動産・住宅分野の取り組み企業
不動産・住宅分野では、空き家や遊休不動産を活用したリノベーション事業が地方創生の重要な柱となっており、地域コミュニティの再生に大きく貢献しています。
株式会社LIFULLは空き家問題に特化し、調査・人材育成・ノウハウ提供・資金調達支援の4側面でサポートしています。
リノベる株式会社は、築48年の電話局を地域参加型複合施設「BOIL」として再生したほか、築45年の元鉄工所をスポーツコート・カフェレストラン・バー・物販テナントを備えた複合施設にコンバージョンするなど、地域資源を活かした再生を進めてきました。
また、複数社が「熱意ある地方創生ベンチャー連合」に参画し、物件改修にとどまらない総合的なまちづくりに取り組んでいます。
事例(3)人材・雇用創出分野の企業事例
人材・雇用創出分野では、マッチングプラットフォームと人材育成プログラムを組み合わせた企業が、地方の人材不足解決と都市部人材の地方進出を同時に実現する重要な役割を果たしています。
ランサーズ株式会社は日本最大級のクラウドソーシングサイトを運営し、「エリアパートナープログラム」を通じて地方自治体でのスキルアップ講習や受注者育成プログラム、移住促進ワークショップを開催してきました。
2014年に各都道府県に設置された「よろず支援拠点」は、中小企業の経営課題にワンストップで対応する相談窓口として機能し、支援機関が多数存在する中での窓口一本化を実現しています。
また、地域おこし協力隊制度を活用した人材確保や、大学・高専との連携による地域人材育成の取り組みも各地で展開されており、継続的なスキル開発支援と地域定着促進の仕組み構築が重要となっています。
事例(4)農業・1次産業支援企業
農業・1次産業支援分野では、スマート農業技術とアグリテック企業が生産性向上と後継者育成の両面で地方創生に積極的に貢献しています。
大手企業からベンチャー企業まで幅広い事業者がアグリテック分野に参入し、AI・IoTを活用した生産管理システム、ドローンによる圃場監視、自動化された栽培システムなどを提供して農業の効率化を支援しているのです。
建設業界でも地方創生への取り組みが活発で、岐阜県飛騨地方では建設会社が林業を手がけ、愛媛県では建設会社が農作業を支援するなど、建設業のノウハウを活かした地域の労働力不足解決が進んでいます。
地域の特産品を活用した6次産業化支援や、EC・CRMシステムの導入による販路拡大支援も重要な役割を果たし、技術導入だけでなく地域の農業従事者との信頼関係構築と継続的な技術サポート体制の整備が成功の鍵となっています。
\ 長野県求人数No.1 /
地方創生の成功・失敗事例から学べること


この章では、企業の成功・失敗事例を分析し、実務に生かせる学びを整理します。
参入が加速する中で、成功と失敗を分ける要因の理解がいっそう重要です。
- 成功企業と失敗企業の決定的要因の比較分析と共通パターンの抽出
- 失敗事例から導き出される具体的なリスク回避策と予防対策
- 成功事例の再現可能性と他地域・他業種への応用方法論
分析(1)成功企業と失敗企業の決定的要因
成功の鍵は、地域との信頼関係と、持続可能な収益モデルの両立です。
アソビュー株式会社は、鳥取県での「体験×WEB」を足がかりに横展開を進めました。地域の文化や特性を理解し、住民協働を重視したことが継続的な成長につながりました。
一方、短期志向や補助金依存に陥ると、制度変更に左右され継続が難しくなるリスクがあります。
また、企業間の知見共有(例:「熱意ある地方創生ベンチャー連合」)により、地域へのコミットと事業の持続性を両立しやすくなります。
分析(2)失敗事例から学ぶ具体的な回避策
地方創生事業の失敗パターンは予測可能な要因が多く、適切なリスク管理により回避できるケースが大半を占めています。
よくある失敗は、社会的KPIと事業KPIの分断、住民合意の不足、観光の一極集中(オーバーツーリズム)、人材流動による継続困難、補助金依存による自立性の欠如などがあげられます。
回避策として、二階建てKPI(社会と事業の両立)、段階的スコープ管理による合意形成、利益配分の透明化、データに基づく混雑分散、撤退基準の事前設定が有効です。
老朽システム刷新や人手不足を見据え、デジタル技術で課題解決プロセスを効率化することも成功要因です。
分析(3)成功事例の再現可能性と応用方法
成功事例は地域特性を踏まえた適切なカスタマイズにより、他地域への応用が十分に可能です。
地方創生の成功要因は、地域固有の要素と汎用的な要素に分類でき、汎用的な部分は他地域でも再現可能です。
ソフトバンクの「ぱわふる」プラットフォームは、自治体DX推進の標準的なソリューションとして全国の地方自治体で活用されており、ランサーズの「エリアパートナープログラム」も、フリーランス活用という汎用的な仕組みを各地域の特性に合わせてカスタマイズする成功モデルとなっています。



建設業界でも、岐阜県飛騨地方の林業参入や愛媛県の農作業支援など、建設業のノウハウを活かした地方創生モデルが他地域に展開されています。
成功企業との連携やノウハウ共有の機会を積極的に活用することで、リスクを最小化しながら効果的な事業展開が可能です。
\ 長野県求人数No.1 /
企業が地方創生に取り組むメリット


この章では、企業が地方創生に参入するメリットを整理します。
政策支援や評価制度の整備が進むなか、企業にとっての利点は多様化しています。
- 企業ブランディング・CSRの向上(市場競争力の強化)
- 優秀な人材確保と採用力強化による組織力向上
- 新市場開拓と事業拡大機会による収益源の多様化
- 税制優遇と補助金活用による財務メリットの最大化
メリット(1)企業ブランディング・CSR向上効果
地方創生への取り組みは企業の社会的責任を示し、ブランド価値や顧客ロイヤリティの向上につながります。
現代の消費者は企業の社会貢献度を重視する傾向が強まっており、SDGsへの関心と相まって地方創生企業への信頼度は向上しています。
ローソン株式会社は地域ごとのニーズに応じた商品開発と地元農産物の積極的な取り入れにより、地域貢献企業としての強いブランドイメージを確立しました。
リノベる株式会社は連合への参画を通じ、業界横断の取り組みを牽引し、社会的責任を体現しています。
企業版ふるさと納税を活用することで、税制優遇を受けながら地域貢献をアピールする企業も増加中です。
メリット(2)優秀な人材確保と採用力強化
地方創生に積極的な企業は、社会的意義を重視する人材を惹きつけやすく、採用面で優位に立ちやすくなります。
コロナ禍を経て働き方に対する価値観が変化し、単なる高収入より仕事の社会的意義を重視する人材が増加しました。
ランサーズ株式会社の「エリアパートナープログラム」では、地方自治体でのスキルアップ講習や移住促進ワークショップを通じて、フリーランス人材と地域のマッチングを成功させています。
面白法人カヤックは鎌倉在住者向け住宅手当など、地域へのコミットと人材確保を両立させる制度を運用しています。



地方創生分野では明確な目的意識があるため、モチベーションの高い人材を確保しやすい環境です。
メリット(3)新市場開拓と事業拡大機会
地方創生事業は企業にとって新たな市場開拓の機会を提供し、地域資源を活用した独自性の高いビジネスモデル構築により競争優位性を確立できます。
人口減少地域でも、特色ある商品・サービスへの需要は存在します。都市部にはない資源や文化的価値が競争力の源泉になります。
アソビュー株式会社は鳥取県での「体験×WEB」による地域活性化成功事例を全国に展開し、地方の体験型観光市場を新たなビジネス領域として確立しました。
株式会社trippieceは、テーマ性のある旅行マッチングサービスにより50%以上のリピート率を実現しています。



建設業界では岐阜県飛騨地方での林業参入や愛媛県での農作業支援など、本業のノウハウを活かした事業多角化により新市場を開拓する企業が増加しています。
メリット(4)税制優遇と補助金活用メリット
地方創生分野では企業版ふるさと納税をはじめとする税制優遇制度や、2025年度予算案で倍増予定の各種補助金により、大きな財務メリットを享受できます。
政府は地方創生を国の重要政策として位置づけ、2024年度の関連予算約1053億円に加え、石破首相が2025年度予算案で交付金倍増を表明し財政支援を大幅に拡充しています。
企業版ふるさと納税は、条件を満たせば寄付に伴う税負担を大幅に軽減でき、コストを抑えた地域貢献が可能です。
2024年には従業員2000人以下の中堅企業者向けの新たな支援制度である「中堅企業向け賃上げ促進税制」も創設され、支援対象が拡大されています。
奈良市では企業誘致に最大500万円の補助金を提供するなど、自治体レベルでも企業支援制度が充実しています。
\ 長野県求人数No.1 /
企業が地方創生に取り組むデメリット


この章では、企業が参入時に直面しやすいデメリットやリスクを整理します。
期待が高まる一方、現場の運営には固有の課題があります。
- 初期投資の大きさと回収期間の長期化による財務負
- 地方特有の商慣習や人間関係の複雑さによる事業推進の困難
- 成果測定の難しさと評価基準の曖昧さによる投資対効果の不明確化
デメリット(1)初期投資コストと回収期間の長さ
地方創生事業では多額の初期投資が必要な一方で、投資回収期間が長期にわたるため企業の財務負担が重くなります。
築古物件の再生では、構造調査・耐震補強・設備更新に加え、住民合意形成に時間を要し、回収期間が中長期化しがちです。
建設業界では岐阜県飛騨地方での林業参入において、重機購入、林道整備、技能習得のための初期投資に数千万円を要し、収益化まで3年以上かかった事例があります。
地方での立ち上げは、物流・採用・広報などのコストが高くなりがちです。
計画の見直しが必要な場合に備え、十分な資金計画と長期の事業設計が不可欠です。
デメリット(2)地方特有の商慣習や人間関係の複雑さ
地方では、長年の商慣習や人間関係が強く、外部企業は調整に時間と労力を要することがあります。
世代を超えた関係性や暗黙の取引慣行があるため、新規参入企業は外部者と見なされることがあるのです。



地方創生事業でよくある失敗として、住民合意不足による地域反発、既存事業者との利益相反、自治体内部の部署間調整の困難などが報告されています。
観光分野では、一極集中がオーバーツーリズムを招き、住民との摩擦が生じる場合があります。
参入企業が増えるほど、既存ネットワークとの調整は難しくなります。
地域の歴史・文化への理解と、段階的なスコープ管理で信頼を築くことが重要です。
デメリット(3)成果測定の難しさと評価基準の曖昧さ
社会的成果と事業成果の評価軸が絡み合い、ROIの算出が難しく投資判断が曖昧になりがちです。
地方創生の成果は人口増加、雇用創出、観光客数増加などの社会的KPIと、売上、利益、市場シェアなどの事業的KPIが混在し、どちらを優先すべきかの判断が困難です。
よくある問題として、KPIが社会的成果と事業収益で分断され、社会貢献は達成できたが収益性が確保できない、または収益は上がったが地域住民の満足度が低いといった事例があります。
ステークホルダーごとに重視する評価軸が異なるため、自治体は人口増、企業は収益性、住民は生活の質など、統一的な成果測定基準の設定が困難です。
2025年の崖と呼ばれるDX推進の必要性が高まる中、デジタル技術を活用した効果測定手法の導入も進んでいますが、住民満足や文化価値の保全など、定性的な指標は数値化が難しい点が課題です。
\ 長野県求人数No.1 /
企業が地方創生に参画する方法と支援制度


この章では、企業が参画するためのステップと、活用できる支援制度を紹介します。
予算・制度の拡充により、参画機会は広がっています。
- 企業版ふるさと納税:税負担を抑えた地域貢献の実現
- 自治体との戦略的パートナーシップ構築:継続的な事業基盤づくり
- 地方創生関連の人材市場を活用した専門人材の確保
- 国・自治体の補助金・助成制度を組み合わせた財務支援の獲得
方法(1)企業版ふるさと納税の活用方法
企業版ふるさと納税は、条件を満たせば寄付に伴う税負担を大幅に軽減できる制度です。
自治体の地方創生事業に寄付することで、法人税負担の軽減が見込めます。
「ふるさとチョイス」などのプラットフォームを通じて、幅広い業種の企業が活用しています。寄付額や控除率は制度要件に従い確認が必要です。
自治体側も企業のノウハウや技術を活用した地方創生プロジェクトを企画し、企業の専門性と地域課題をマッチングさせる取り組みが進んでいます。
寄付企業は感謝状や名称の掲示などブランディング効果も見込めます。
自社の事業領域に近いプロジェクトを選び、技術提供や人材派遣と組み合わせると効果的です。
方法(2)自治体との連携パートナーシップ構築
自治体との戦略的パートナーシップ構築には、情報収集から協定締結まで体系的なアプローチが必要です。
まずRESAS(地域経済分析システム)で地域課題を把握し、RFI(情報提供依頼)→RFP(提案依頼)・公募→協定締結の順で進めるのが一般的です。
ソフトバンクの自治体DX推進サイト/取り組み群「ぱわふる」は、標準的なソリューションや事例を整理し、継続的な連携を支えます。
調達形式も一般競争・プロポーザル・随意契約など多様で、それぞれに適した戦略が必要です。
首長部局・企画課・産業振興課・観光課などの役割を踏まえ、地銀や商工会議所も巻き込んだ多面的なアプローチで、持続可能な官民連携を構築します。
方法(3)地方創生関連の求人・転職市場
地方創生関連の人材市場は急速に拡大しており、特に地方創生企業への転職や副業参画は社会的意義とキャリア形成を両立できる魅力的な選択肢として注目されています。



2025年の交付金倍増計画により地方創生事業が拡大する中、DX推進、観光マーケティング、まちづくりコンサルティング、空き家活用などの分野で即戦力人材が求められています。
ランサーズ株式会社の「エリアパートナープログラム」では、フリーランス人材と地方自治体のマッチングを成功させ、副業形態での地方創生参画モデルを確立しました。
地域おこし協力隊制度も活用が進み、都市部の優秀な人材が地方に移住して地域活性化に取り組む事例が増加しています。
テレワークの普及により地方在住でも都市部企業との関わりが可能になり、働き方の選択肢が多様化している状況です。
方法(4)国・自治体の補助金・助成制度
補助金・助成制度の拡充により、複数制度を組み合わせて事業費をカバーしやすくなっています。
石破首相による交付金倍増計画に加え、2024年には従業員2000人以下の「中堅企業者」向けの新制度も創設され、支援対象が大幅に拡大されました。
主要な制度には、地域未来牽引企業、地方創生関係交付金、IT導入補助金などが挙げられます。
自治体独自の支援もあり、例えば奈良市の「奈良市サテライトオフィス等設置推進補助金」を活用すれば上限500万円、本社設置で100万円加算で最大600万円の補助金を受け取ることが可能です。
2014年に各都道府県に設置された「よろず支援拠点」では、ワンストップでの相談対応により複雑な支援制度の活用をサポートしています。
デジタル地方創生サービスカタログでは優良な実装事例が共有され、効果的な制度活用方法も紹介されています。
\ 長野県求人数No.1 /
まとめ





本記事では、地方創生に挑戦する企業向けに、分野別の成功事例から失敗を回避するノウハウ、具体的な参画方法までを網羅的に解説しました。
成功の鍵は、資金力や技術力だけではなく、地域課題への深い共感と、住民や自治体を巻き込む「共創」の姿勢にあります。
自社の論理を一方的に持ち込むのではなく、地域に根差した持続可能なビジネスモデルを描けるかが成否を分けます。



この記事を参考に、自社の強みを活かせる領域を見定め、企業版ふるさと納税などの制度も活用しながら、地域との対話という確かな一歩を踏み出してください。